- 2025年6月9日
- 5 view
七五三撮影と本番を別々に!~余裕を持たせたスケジュールのすすめ~
七五三撮影と本番を別々にするメリットとは? 七五三は、子どもの成長を祝う大切な日本の伝統行事です。毎年11……
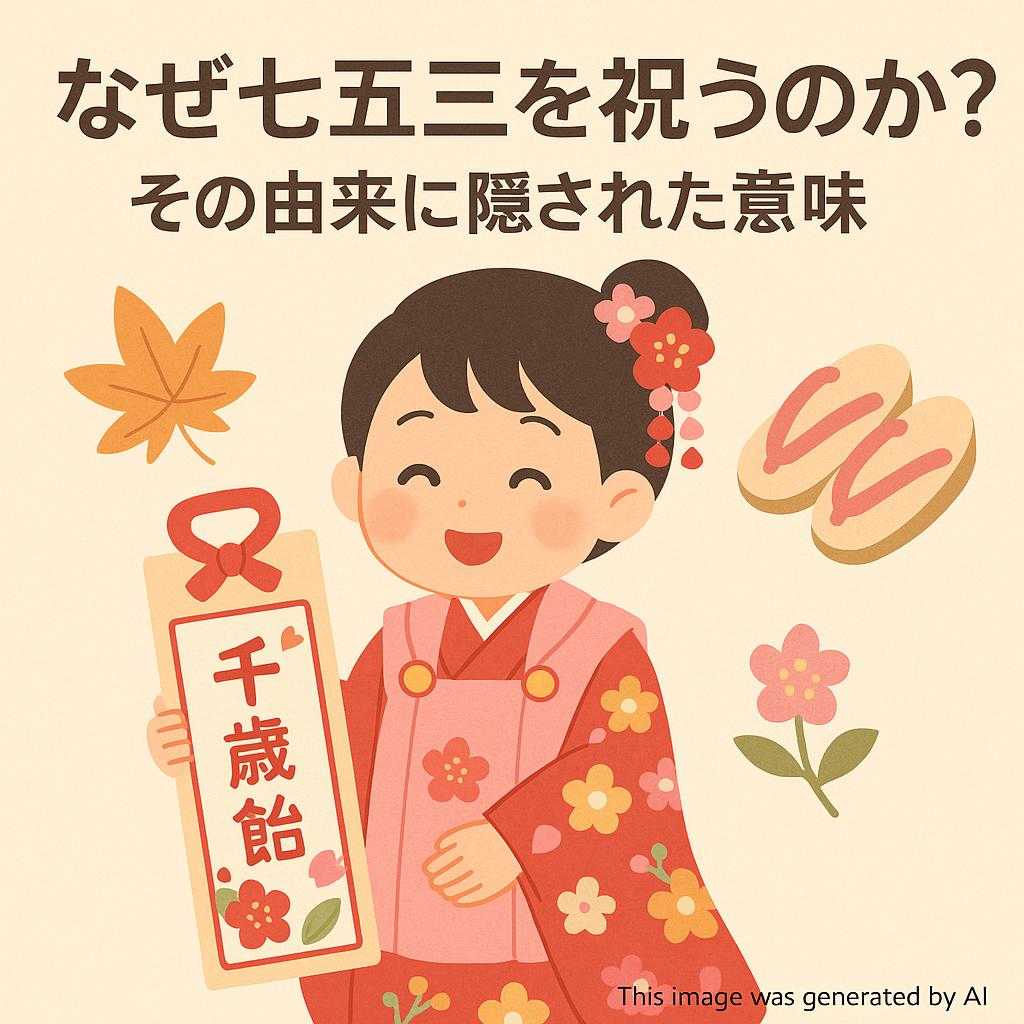
七五三は、日本の伝統的な年中行事で、子どもの成長を祝う特別な日です。この行事は7歳、5歳、3歳の子どもを対象に行われ、主に家族が神社や寺院を訪れ、子どもの健康と成長を神様に感謝し、今後の無事を祈る機会となっています。この風習は平安時代から続くものであり、その歴史や意味には深い文化的背景があります。
七五三という名称は、それぞれの年齢に由来しています。古代日本では、子どもがこの年齢に達することが一つの節目とされ、特に重要視されていました。3歳は髪置きの儀式、5歳は袴着の儀式、7歳は帯解きの儀式が行われ、それぞれが子どもの成長段階を象徴しています。これらの儀式は元々貴族や武士階級で始まりましたが、江戸時代には庶民にも広まりました。
なぜ七五三を祝うのか?その理由
七五三を祝う理由は単なる年齢のお祝いだけではありません。これは日本文化に根付いた信仰心や家族愛を反映しています。古来より、日本人は自然との調和と共生を重んじており、その中で生命の誕生や成長も特別な意味を持っていました。七五三はそのような価値観から生まれた行事であり、現代でも多くの家庭で大切にされています。
このようにして、七五三には深い意味と歴史があります。毎年11月15日頃、多くの家族が子どもの健やかな成長を願って神社へ足を運びます。この伝統的な行事は、日本文化の豊かさと家族愛を再確認する貴重な機会です。
七五三は、日本の伝統的な行事であり、子どもの成長を祝う特別な日です。この行事は、3歳、5歳、7歳という年齢に達した子どもたちを対象に行われます。では、なぜこれらの年齢が選ばれたのでしょうか?その由来には深い意味が隠されています。
まず、七五三の起源は平安時代に遡ります。当時は子供の成長を祝うための儀式がいくつか存在しました。具体的には、3歳で「髪置き」、5歳で「袴着」、7歳で「帯解き」という儀式が行われていました。これらの儀式は、それぞれの年齢における成長と変化を象徴しています。
髪置きとは、3歳になるまで剃っていた髪を伸ばし始めることを指します。この習慣は平安時代から続いており、子どもが無事に成長したことを神様に感謝する意味があります。この時期には特別な衣装を着せて神社へ参拝し、健康と長寿を祈ります。
5歳になると男児は初めて袴を着用します。袴着の儀式は武家社会で特に重要視されていました。この年齢になると、一人前として扱われ始めるため、その節目を祝う意味があります。現代でも多くの家庭で男児が袴姿で神社参拝する姿が見られます。
7歳になると女児はそれまで使っていた紐付きの着物から、本格的な帯付きの着物へと移行します。この帯解きという儀式は、少女から一歩大人へ近づくことを象徴しており、大切な節目として祝われています。

七五三の日付として一般的には11月15日が選ばれています。この日は江戸時代、第5代将軍徳川綱吉が自身の息子徳松(後に綱吉)の健康祈願として定めた日と言われています。また、この日は旧暦で鬼が出歩かない吉日ともされていました。そのため、多くの家庭ではこの日に合わせて神社参拝やお祝いを行います。
現代では七五三のお祝い方法も多様化しています。伝統的な神社参拝だけでなく、写真館で記念撮影をする家庭も増えています。また、お祝いの日程についても柔軟になりつつあり、多忙な家庭では週末や祝日に合わせて行うことも一般的です。
さらに、お祝い後には家族や親戚が集まり食事会を開くこともあります。このようなお祝い方法によって家族間の絆が深まり、子どもの成長をみんなで喜ぶ機会となっています。
七五三は日本文化に根付いた大切な行事です。その由来や意味を理解することで、このお祝いがどれほど深い意義を持っているか再認識できます。古来から続くこの伝統行事は、今後も多くの家庭で受け継がれていくことでしょう。そして、その背景にある歴史や文化への理解が深まることで、一層豊かな体験となります。

七五三の由来は平安時代に遡ります。当時の貴族が子供の成長を祝うために行っていた儀式が始まりです。特に、3歳、5歳、7歳の節目に行われる儀式として定着しました。この伝統行事は、子供たちが無事に成長することを願い、その健康を祈る目的で続けられています。
11月15日に七五三を祝う理由にはいくつかの説があります。その一つは、江戸時代に徳川家の将軍がこの日に子供の健康祈願を行ったことからと言われています。また、この日は日本の暦で「二十八宿」の「鬼宿日」にあたり、新しいことを始めるには最適な日とされていました。
七五三では、「髪置きの儀」、「袴着の儀」、「帯解きの儀」といった伝統的な儀式が行われます。3歳では「髪置き」、5歳では「袴着」、7歳では「帯解き」が主な儀式です。それぞれの年齢で異なる意味を持ち、男児と女児で異なる部分もあります。
現代でも七五三は重要な家族行事として多くの家庭で祝われています。この行事は単なる伝統としてだけでなく、お子様自身が家族から愛されていることを実感し、自己肯定感を高める機会ともなっています。また、写真撮影や神社への参拝などを通じて家族全員でお祝いすることで、一層深い絆が生まれます。
七五三のお祝いには、衣装選びや神社への参拝準備などがあります。特に衣装については、伝統的な和装を選ぶ家庭も多く、その際には着付けやヘアメイクも考慮する必要があります。また、多くの場合、写真撮影もセットで考えられており、そのための日程調整や予約も重要です。
七五三のお祝いには、お子様の健やかな成長と健康長寿への祈りが込められています。これは過去において医療環境が十分でなかった時代から続く、大切なお祝いです。現代でもその精神は受け継がれており、お子様だけでなく家族全体が幸せになるための日として位置づけられています。

七五三は、日本の豊かな文化と歴史を象徴する大切な行事です。この行事は、3歳、5歳、7歳という特定の年齢で子どもの成長を祝うものであり、それぞれの年齢に応じた儀式が存在します。平安時代から続く「髪置き」、「袴着」、「帯解き」の儀式は、子どもの成長を神様に感謝し、その健康と未来を祈願する意味が込められています。11月15日という日付もまた、歴史的背景と吉日としての意味があるため、多くの家庭でこの日に合わせてお祝いが行われます。
現代では、七五三のお祝い方法も多様化しつつあります。伝統的な神社参拝に加え、写真撮影や家族での食事会など、新しい形で祝う家庭も増えています。このようなお祝いを通じて、家族間の絆が深まり、お子様自身も愛されていることを実感できる貴重な機会となります。七五三は単なる伝統行事ではなく、日本人の文化的価値観や家族愛を再確認する大切な時間です。この行事が持つ深い意義を理解し、大切に受け継いでいくことが求められます。
💻24時間受付中!WEBからご予約はこちら